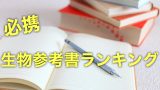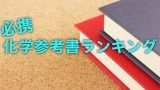この記事を読むと、こんなことが分かります。
東京都板橋区の閑静な住宅街にキャンパスを構える帝京大学医学部。
日本有数の学部数を持つ総合大学である帝京大学の中でも、抜きんでて優秀な学部の一つでもある。
特殊な試験形式でも有名で、ここを知っておくだけでも帝京大学医学部合格率は上がります。
帝京大学医学部を詳しくかつ最高に分かり易く、現役医学生の視点から徹底解剖していきます。
帝京大学医学部はざっくりこんな大学

帝京大学医学部を解剖するなら、歴史が必須。
ということで簡単に帝京大学医学部の歴史を紹介。
帝京大学は1931年(昭和6年)に冲永荘兵衛が東京府渋谷町(現・東京都渋谷区)に創立した財団法人帝京商業学校を起源とする。1966年(昭和41年)に産婦人科学の博士(医学)である冲永荘一により帝京大学が創設された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
帝京大学そのものは帝京商業学校(今で言う商学部)から始まった大学で、2020年現在で創立89年を迎える歴史ある大学。
創立者は意外にも医学者である沖永荘一先生で、産婦人科の医学博士だった模様。
医学部自体は1971年設立で2020年現在、設立49年目。比較的新しい医学部であることが分かりますね。
大学自体を立ち上げたのが医学者であったことから、89年経った現在でも帝京大学医学部は、医療系の研究には相当力を入れていて、医学界でも結構名前を馳せているほど。
10学部32学科からなる、日本有数の総合大学で、経済学部や法学部などの看板文系学部はもちろん、医学部のある板橋キャンパスには薬学部や医療技術学部が一緒に設置されています。
帝京大学医学部の特徴

総合大学である
帝京大学医学部の特徴はなんといっても総合大学の中の一学部であるというところ。
10学部にもわたる多彩な学部を持ち、低学年の時期は医学部以外の学部とも交流を重ねながら、学部横断的な学びができる医学部と言えます。
加えて、他学部との交流が大学内で行えることから、インカレ(学部の垣根を超えたサークル活動)が発達しており、低学年の間はいわゆる華やかな大学生活を送ることができると思われます。
そして同じキャンパス内に薬学部と医療技術学部が共存しているというのも非常に特徴的。
高学年になってからも、将来医療職として職場を共にするかもしれない人たちと交流することができるという素晴らしい環境にあります。
もしも単科大学であれば、医学部のみもしくはあっても看護学部併設ぐらいで、臨床検査系や薬学系の方と交流する機会がないことを考えると、恵まれた環境であると言えるでしょう。
キャンパスが綺麗
後述しますが、帝京大学医学部のキャンパスは板橋区の閑静な住宅街に位置していますが、相当立派です。
そして、他の大学の医学部生がうらやましく思ってしまうほどの、きれいなキャンパス。

敷地面積こそ広くはありませんが、東京都内の大学医学部ではかなり珍しいグラウンドとテニスコートを整備。
医学部の講義棟はもちろんのこと、大学付属病院がめちゃくちゃでかいです。
これだけ広く、きれいなキャンパスであれば相当勉強が捗ることでしょう。
24時までOPENの図書館がある

帝京大学医学部の図書館は、なんと24時まで開館。
実はこれ相当なアドバンテージで、医学部生は想像以上にハードな勉強生活を送ることが定番ですが、たいていの大学医学部の図書館は22時までの開館が多い。
そんな中、24時まで空いている勉強環境が整っているというのは、かなり恵まれていると考えられます。
つまりは、他大学の医学部生よりも二時間長く勉強に費やすことができるということであり、勉強環境としては最高であると言えます。
大学病院の設備が充実
医学部における命といっても差し支えない、附属病院。
その中でも、帝京大学医学部の附属病院は最高クラスの医療環境と教育環境を兼ね備えています。
まず、病床数が1154床。この数字はかなり大きい方なのですが、どれほど大きいかというと、東京都内においては東京大学、東京女子医科大学に次ぐ三番目の多さ。
病床数が多ければ多いほど、多彩な病気を学ぶことができるため、これは大きなメリットとなります。
そして、教育環境では、最新の医療設備が整っており、最先端の医療を間近で学ぶことができます。
さらには、東京大学などからやってきた優秀な教員から直接教えてもらえるために、教育環境としても充実していると言えます。
帝京大学医学部にいってみた
さて、ここまで帝京大学医学部について解説してきました。
このコーナーでは、帝京大学医学部がどんな大学なのか、そしてどんなキャンパスなのかもっと具体的に想像できるようにおGちゃん(筆者)が実際に行ってみたので、その様子をお伝えしたいと思います。

帝京大学医学部の設置されている板橋キャンパスは、東京都板橋区加賀にあり、最寄り駅は十条駅。

駅前の雑然とした通りから、閑静な住宅街を通り抜けていくと突然現れる金麦色の巨大な附属病院と関連施設。

正面から見ると、明らかにきれいなガラス張りの施設と、帝京大学医学部附属病院の大きな看板が見えてくる。
ちなみに、写真からではあまり伝わらないかもしれないが、病院の規模がけた違いに大きい。
広さはさることながら、高さが相当あり、一番上にはヘリポートも設置されており、で相当な規模感に圧倒された。
後で調べてみると83.5mもの高さ(世界一高い木造ビルと同じ高さ)があったようで、道理で大きく感じたわけが分かった。

もちろん、大学病院だけでなく大学の校舎自体も相当な規模で、私がこれまで行ってきた大学の中では最高クラスに大きかった。
しかも、めちゃくちゃきれい。
ちなみに、大学病院の一階にはナチュラルローソンとドトールコーヒーが入っており、使い勝手は良さそう。
そして、驚くことなかれ。
なんと、医学部棟の一階には「ケンタッキー・フライド・チキン」、「イタリアントマトカフェジュニア」、「ファミリーマート」「サブウェイ」といった名だたるチェーン店が入っている。
実際のところ、私はこの光景を始めてみたときにはビビってしまった。
『え!?大学内にこんなにいっぱい有名チェーン店があるのか??」と。
その通りで、帝京大学医学部に入れば、こういったおしゃれでいい感じなお店を毎日のように利用することができる。
なんと贅沢な。
しかもしかもおしゃれな大きい本屋さんまで併設している。
もう言葉が出ないほどなのだが、圧倒的な規模感と、その贅沢な空間のつくりはさすが帝京大学医学部。

附属病院内にも用事があって入ってみたが、中は相当綺麗。
病院と医学部棟をつなぐ渡り廊下もあり、かなり便利そうだった。
今回行ってみた感想をまとめてみるとこんな感じ。
帝京大学医学部の偏差値は?
帝京大学医学部の偏差値は2020年現在、河合塾全統模試で
一般入試:65
センター利用入試:65
となっています。
全国の医学部内では実に平均的な偏差値であると言えるでしょう。
つまりは、医学部に入りたいという人なら、着実な努力を重ねれば決して入ることのできない大学ではなく、志望校として視野に入れるという選択は良い選択と思います。
ましてや、これだけ充実の設備を持つ大学ですから、入って後悔することはまずないでしょう。
帝京大学医学部の学費は高いのか?
2020年度入学者の6年間納入金は
39,380,140円
※初年度納入金:9,370,140円、二年次以降各年納入金:6,002,000円として計算 なお、帝京大学入試情報サイト(https://www.teikyo-u.ac.jp/applicants/exam/payment_medical/)を参考に当サイトが集計
という金額になりました。
なお、この金額は全国の31ある私立医学部の中では四番目に高額であり、相当な学費がかかることを意味しています。
つまりは帝京大学医学部にどうしても通いたいという場合はそこそこ高額な金額を支払う必要があることが分かります。
ただし、前述のとおり帝京大学医学部の設備、教育環境は全国でもトップクラスであり、これだけの学費がかかるということも納得できますし、むしろこれだけ環境が整っているのならこれだけの学費がかかるのは妥当ではないかと考えられます。
帝京大学医学部の学費は、私立医学部の中ではかなり高額
教育設備・環境が整っているため、維持費を考えると高額であっても妥当
帝京大学医学部の入試形式
入試形式(2020年度)
| 形式 | 募集人数(人) |
| 一般入試 | 92 |
| 一般入試(特別枠) | 8 |
| 推薦入試 | 8 |
| 推薦入試(福島県枠) | 2 |
| センター利用入試 | 10 |
| 計 | 120 |
| ※一般入試特別枠は千葉県が5名、静岡県が2名、公衆衛生研究医養成枠が1名 | |
| 推薦入試福島県枠は2名 | |
| ※情報はhttps://www.teikyo-u.ac.jp/applicants/pdf/exam/download/07.pdfより引用 当サイトまとめによる |
帝京大学医学部の入試形式解説
グラフでも示したように、帝京大学医学部の入試形式は大きく分けて三種類。
一般、推薦、センター利用の三つになります。
その中でも一般と推薦には地域特別枠と、研究医枠が設けられており、特別な修学資金貸付制度(いわゆる奨学金)が設定されています。
これらの制度は、『合格し帝京大学医学部を卒業した暁には、それぞれの地域で数年間働きます』ということを約束したうえで、修学資金を一定金額借りることができる制度です。
この制度を利用することで、一定の条件がありますが、少々低額で帝京大学医学部に入学、通学することが可能です。
ただし、試験難易度自体は変化しないので、入学難易度自体が変化するわけではないので注意してください。
センター利用入試は、その名の通りセンター試験を利用した形式の試験で、センター試験を受験する場合は、こちらの受験形式も出願することをお勧めします。
各入試形式の合格最低点(2019年度統計)
| 入試形式 | 合格最低点 | 得点率 |
| 一般入試 | 212/300 | 70.6% |
| センター利用入試 | 504/600 | 84% |
※https://passnavi.evidus.com/search_univ/2700/border.htmlより引用
このデータからは、一般入試のボーダーが7割前後、センター利用(今後は全国統一大学入試に変更)入試が8割4分であることが読み取れます。
センター利用については、科目を絞って受験することでかなりの高得点をたたき出すことが可能なため、非常に挑む価値の高い入試形式であると言えます。
※2021年度入学試験より、センター試験が廃止されるため一定の変化が見込まれます。最新の情報に注意してください。
帝京大学医学部の入試形式はここが特殊!!
まず、他の医学部に関しては一般入試において、一次試験を1日のみに設定している場合が多いですが、帝京大学医学部は一次試験を自由に選択できる3日間のうちで受験することができるようになっています。
つまり、3日間の中から好きな日程を選んで受験することが可能というわけです。
と、実はここからが特殊で、帝京大学医学部の一般入試は何と3日間すべてを受験するということも可能になっています。
つまりは3回もチャンスがあるということです。
加えて、複数日受験した場合は、そのうち最も得点率が高かった試験の得点が合否判定に使用されます。
つまり、一番コンディションのいい時の成績を合否判定に使ってもらうことができる、ということです。
3日間すべて帝京大学医学部を受けることにするもよし、2日、もしくは1日だけ受験して、他の日程を他の医学部受験に充てることもよし。
非常に柔軟な受験が可能になっています。
帝京大学医学部の入試攻略
各科目難易度
| 英語 | 数学 | 化学 | 生物 | 物理 | |
| 難易度 | 標準 | 標準 | 標準 | やや難 | やや易 |
| 形式 | マーク | 穴埋め | 記・穴 | 記・穴 | 記・穴 |
| ※国語はデータなし |
※データはhttps://www.melurix.co.jp/kouryakuhou/255/より引用
一般入試、センター利用入試は3科目から2科目選択
帝京大学医学部の入試科目は、全国私立医学部で稀に見る「国語」が含まれており、この点において非常に特徴的だと言えます。
一般入試、及びセンター利用入試では、国語、数学、理科(物・生・化から2つ選択)の3科目から2科目を選び受験することが可能になっています。
つまりは、自分の得意な科目のみを選択して受験するということも可能であり、元文系志望の方でも、努力次第では帝京大学医学部に合格することが可能です。
英語(必須)、国語、理科という選択も可能で、数学が苦手であるという方でもかなり入学の可能性を高めることができます。
入試攻略方法
理科
まず、理科を選択する場合、差がつきやすいという意味で生物選択がお勧めです。
物理はやや易というレベルの難易度で、比較的点数を取りやすいということが考えられます。
つまり、受験生みんながまんべんなく点数を取ることができるということ。
逆に言えば、少しでもミスをすれば他の受験生との大きな差につながりかねません。
したがって、物理が苦手な場合はあまり物理を選択することは得策ではないでしょう。逆に生物はやや難というレベルの難易度で、生物がもしも得意なのであれば、周りと差をつけることができます。
コンマ数点が合否を分ける医学部受験において、少しでも自分が点の取りやすい科目を選択することは非常に大切です。
また、化学、生物、物理全科目共に、記述及び穴埋め形式ですから、事前に過去問を解くのはもちろんのこと、しっかりとした記述にも対応できるように、常日頃から参考書などを使って論理力を磨いておくことも重要です。
また、生物の勉強法については別記事で滅茶苦茶詳しく解説していますので、そちらも合わせて読んでください。
数学
穴埋め式であるということが特徴的です。
穴埋め式の試験の対策は、これまで行われてきたセンター試験数学を解きまくること。
そして、他の医学部、他学部の穴埋め形式の問題を解きまくることです。
数学は特に、ひらめきの前に必ず暗記を必要とする科目ですから、網羅系の参考書から取り組み、次第に応用へとつなげていくことをお勧めします。
もちろん、数学の基礎ができていないならば、まずは基礎をしっかり固めていかなければいけません。
特に帝京大学医学部では微・積分や数列、ベクトル、確率が頻出ですので、過去問演習の前には確実に基礎を押さえて取り組むことが必要です。
基礎的な問題集を周回することはもちろん、応用を利かせることができるように、何度も何度も繰り返し問題集を解いていくことが必要でしょう。
国語
正直に言って、私立医学部において国語を入試科目として採用している大学は全国見渡しても帝京大学医学部ぐらいです。
ですから、他大学にも似た問題が出るわけもなく、非常に対策が難しいと考えられます。
もちろん、センター試験形式の文章題が解けるようになることは当たり前のこと、さらにその上の応用力を身に着けるには、細かい単語の意味を覚える、文章の細部まで構文として理解する、などの努力が必要になってきます。
もちろん、帝京大学医学部自身の過去問は公開されていますから、自分で分析して似た傾向の文章を読み込んだり、読解に取り組んだりといったことが大切になってきます。
英語
どの大学でも今や必須の科目となった英語ですが、帝京大学医学部でも例外はなく、たとえ英語が苦手であろうが、お構いなしに英語が必要になってきます。
帝京大学医学部の英語はマーク式、しかもさほどスピードを要求される試験ではありません。
したがって、センター試験の過去問、帝京大学医学部の過去問を解くということが最も有効な対策法であると考えられます。
もちろん、英文は時間をかけずに読めるに越したことはないため、速読の力は必要になってきます。また、医学的な単語を押さえておくというのも対策の一つでしょう。
特に、帝京大学医学部の場合、必須受験になっているため、英語の成績が他の受験生との差に直結する科目と言っていいでしょう。
できるだけ自分に合った勉強法で、かつ自分の身に合った参考書を使って勉強していくことが必須であると言えます。
まとめ
帝京大学医学部は、私立医学部の中でもかなり設備が整っており、そのため比較的高額な学費になっていますが、それを補って余りあるだけの環境の良さがあります。
また、入試形式も、再受験生や元文系の方にやさしめの試験であり、私立医学部を受験するならば、志望校に加えておきたい医学部でもあります。
合格への一歩は大学を知るところから。
是非ともこの記事を隅々まで読み込んで、日ごろから努力を欠かさないようにしてください。



今回の私立医学部を知る、は日本大学医学部について解説していきます!!大人気行ってみたコーナーをはじめ、日本大学医学部を知りたい皆さんのための情報が満載!!