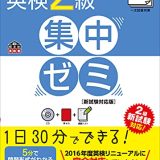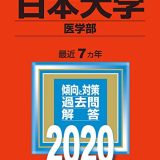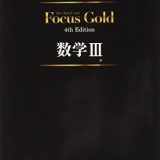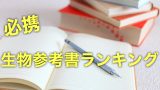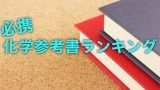この記事を読むと、こんなことが分かります。
東京都板橋区の閑静な住宅街にキャンパスを構える日本大学医学部。
日本有数の学部数・生徒数を誇る総合大学である日本大学の中でも、抜きんでて優秀な学部の一つでもあります。
同難易度の医学部は関東圏、関西圏に多く存在しますが、日本大学医学部でしか経験しえない、特徴的なコトがあります。これを知っておくだけでも日本大学医学部の合格率は上がります。
日本大学医学部を詳しくかつ最高に分かり易く、現役医学生の視点から徹底解剖していきます。
日本大学医学部はざっくりこんな大学

日本大学医学部を詳しく知るなら歴史が必須。
ということで、少しだけ歴史をご紹介。
国家神道を確立するべく、皇道を広く国民に教化し、神職資格を与える養成機関として発足した皇典講究所を母体とする。法体系の編修が急がれ、もともとは講究施設である國學院に国法を創設するつもりであったが、その国法科を日本法律学校と名乗ることとした。1898年(明治31年)3月に高等専攻科を設置。財団法人となり分離独立し、文理学部の前身となる高等師範科を設置。1903年(明治36年)に日本大学と改めた。翌年、専門学校令に基づく大学、経済学部と商学部の前身となる商科を設置。1920年(大正9年)、大学令認可となる。この頃、私立大学の中では初めに女子の入学を認めた。6月、理工学部の前身となる高等工学校を開設。翌年、芸術学部の前身となる美学科を設置。翌月には、歯学部の前身となる歯科医学校を開校。その4年後に医学部の前身となる専門部医学科も設置。
日本大学 - Wikipediaより引用
少々長いですが、この情報によると日本大学自体の歴史は2019年現在で121年と非常に歴史ある大学となっています。
医学部だけであっても、設置が1925年であり、94年もの長い歴史を誇る医学部となっています。
なお、日本大学自体の話になりますが、16学部87学科を有しており、日本の私学におけるマンモス校として全国にその名を轟かせています。
日本大学医学部の特徴

総合大学である
日本大学医学部の特徴は、何といっても全国屈指の総合大学であるというところ。
良くも悪くも、全国的に名の知れた大学で、日本大学自体のキャンパスは全国に点在しています。
全学を合わせれば、軽く6万人以上の学生が在籍しているので、もはや一つの町や村レベルで人がいることになります。
さらに、医療系の学部に限った話でいえば、医学部、薬学部、獣医学部がそれぞれ1つずつ、加えて歯学部が2つ設置されており、非常に多彩な構成になっています。
これは、自然科学系の他の大学が学部の多さをうらやましがるレベルです。それほどまでに多くの学問を学べる、希少な大学であるといっていいでしょう。
非常に先進的なカリキュラムで学ぶことができる
また、カリキュラム上では日本大学の建学理念である「自主創造」を体現するための教科が多くあり、自力で歩んでいくことのできるのに十分な知識、教養を身につけることができます。
加えて、日本で初めて「OSCE」という臨床試験を導入したことで知られており、医学部の世界においては非常に先鋭的な存在となっています。
医学部においては『 醫明博愛 』という精神の元、医学教育が行われており、着実な医学知識の定着と、高い人間力を持った医師の育成が進められています。
加えて、日本で初めて「OSCE」という臨床試験を導入したことで知られており、医学部の世界においては非常に先鋭的な存在となっています。
長い歴史を持ち、卒業生が多い
『ざっくり紹介のコーナー』でも述べた通り、日本大学医学部は1925年に設置され、2020年現在で95年もの長い歴史を持つ医学部の一つです。
これだけ長い歴史があれば、卒業してきた人数もかなり多く、すでに何千人ものハイレベルな医学者、医者を輩出していることもお分かりになるでしょう。
そして、現役医学部生の視点から見ると、これは結構なメリット。
なぜかというと、医師としての自分のキャリアモデルを見つけやすくなるからです。
例えば、大学卒業後に海外留学をしたいと思ったり、地域医療に全力で挑み続けて地域を支えていきたいと思ったり。
そういう時に、身近に経験をしたことのある人間が多くいるというものは心強いものです。つてを使って早くから興味のある医療現場の見学、勉強に行くこともできますし、
何より、多くの卒業生の先輩方から、自分が目指したいと思う道を見つけてくることができるというのは非常に大きなメリットとなります。
キャンパス内に運動設備が充実している
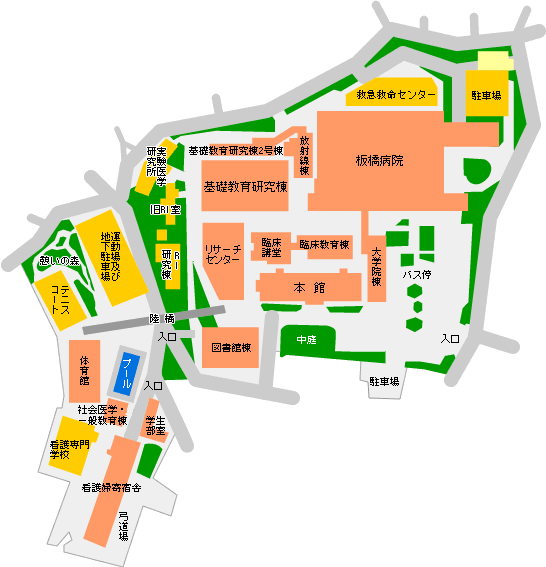
単科の医学部では通常、敷地面積が狭いために敷地内に十分な運動設備が整っていないことが多いのですが、日本大学医学部は比較的広い敷地を保有しているため、プール、運動場、弓道場、体育館、テニスコートなどの大型設備が多数揃っています。
そのため、大学の敷地内で部活動を完結させることができ、非常に効率的に時間を使うことができます。
また、敷地が広い割には比較的コンパクトにまとまっている上、自然も豊かなためリフレッシュもしやすいと考えられます。
ちなみに、敷地内に十分な運動設備がない大学では、外部の運動設備を借りることになり、移動費用だけでも馬鹿にならない金額がかかってきますし、何より時間がかかるので、非常に非効率的になることが多いです。
日本大学医学部に行ってみた
ここまでは、日本大学医学部について解説してきました。
このコーナーでは、日本大学医学部がどんな大学なのか、そしてどんなキャンパスなのかおGちゃん(筆者)が実際に行ってみたので、その様子をお伝えします。

日本大学自体は、多数の学部を有するため非常に多くのキャンパスが存在。
今回は日本大学医学部の紹介ということで、少し都会の喧騒から離れた日本大学板橋キャンパスへ。
東武東上線の大山駅から徒歩約15分、駅前の商店街を通過し、閑静な住宅街を通り抜けると、突如として開けた土地が現れる。
『日本大学医学部』という看板と、板橋病院、看護専門学校などの文字も見えてきた。

近年は、どの大学も(最近では関西医科大学が看護学部を設置したことで有名)医学部に附属の看護専門学校を「看護学科」にするのが主流だが、日本大学はそのまま看護専門学校を受け継いでいる。
(大学の意向としては、病院と医学科が敷設されているため学習環境が、そうでない場合に比べ格段に良くなるため看護の受験生からの人気が上がることを見越しているそう。)

正門を入り、右側にどどんとそびえたつのが、日本大学附属板橋病院。
実は日本大学医学部はもう一つ附属病院を保有しており、そちらの名前は『日本大学医学部附属病院』であるから間違えないように。
病院自体は外から見ても老朽化が分かるくらい古く、お世辞にもきれいとは言えない。
ただし、この病院の耐震基準が震度7まで耐えられるに満たない( 東京都の「地震で倒壊する危険性のある建物」に指定された )ようで、直近で建て替えが検討されているそう。
建て替えられれば、新しく最新鋭の病院となることは間違いない。そうなれば、医学科の校舎も新しくなるだろうから、より一層学習環境が良くなることも予想される。
調べてみると、日本大学医学部附属板橋病院は1970年の開院当時からその姿をほとんど変えていないようで、その古めかしさには納得。

板橋病院よりも校門側、つまり手前側には日本大学医学部の大学院棟が。
室外機がむき出しで取り付けてあり、病院棟よりも若干古く見える。
おGちゃん(筆者)はよく台湾に旅行に行くが、熱帯気候に合うように作られた向こうの古めかしい大学校舎とそっくりなつくり。
これまた、お世辞にもきれいとは言えない。


これまで述べてきた通り、またマップを見てもらえばわかるように、やはり日本大学医学部は敷地面積が広い。
これだけ広々としていれば、ストレスなく学生生活を送れそうだと思う。
日本大学医学部の本館は、創立当時から残っている特徴的な建築の一つで、こちらは単に年季が入っているだけでなく、アカデミックさを目肌で感じさせてくれる、『ザ・大学』といった感じの建築。
この写真を撮りに行ったのは大学の休みの日であったため、本館の中を詳しく見ることは断念。


キャンパス内を散歩していると、巨大な運動設備が多数あり、グラウンド、プール、体育館など運動に必要なものは一通りそろっていることが分かった。

特に現役医学部生として最もうらやましいのはプールである。
夏場に涼しく運動できる場所はなかなか存在しない。敷地面積の狭い単科大学や総合大学であっても、医学部だけ切り離されたキャンパスであれば、十分な設備が整っていないことが多い。
とくにプールは、運動設備で真っ先に削られがちな設備であり、これがきちんと整備されているというのはなかなかうらやましい限りである。

大学内は結構広い敷地であるため、自動車も進入できるような構造になっている。
もちろん、二層構造をとっており、歩行者と自動車は分離して通行することになる。
今回、日本大学板橋キャンパスに実際に行ってみたまとめはこんな感じ。
日本大学医学部の偏差値は?
日本大学医学部の偏差値は2020年現在、河合塾全統模試で
A方式:67.5
N方式一期:67.5
となっています。
全国の医学部の中では若干高めの偏差値となっています。
もちろん、全国の医学部自体の偏差値が高めになっていますから、医学部を目指すなら最初から高い学力を保っていなければなりません。
その上で、日本大学医学部に入学・合格したいのであれば、より一層の努力が必要とされるということです。
参考サイト【https://ishin.kawai-juku.ac.jp/exam/deviation/deviation2.php】
日本大学医学部の学費は高いのか?
2020年度入学者の6年間納入金は
33,380,000円
※日本大学医学部公式サイト(https://www.med.nihon-u.ac.jp/gaiyou/gakunoukin.html)を参考にして算出
という金額になっています。
この金額は全国に31ある私立医学部のうち、14番目に安い金額となっています。
より高い大学には東京女子医科大学が、より安い大学には大阪医科大学などがあります。
全国の私立医学部の中では中間ぐらいの金額を維持しており、偏差値などと合わせて考えると妥当か少々コスパが良いぐらいの金額であることがうかがえます。
もちろん、医学部の中でも伝統があり卒業生が多く、環境としても閑静な住宅街の中であり、かつ勉強しやすい環境であることを考えると、非常に安いと捉えることもできるかもしれません。
日本大学医学部の学費は私立医学部の中では平均的で妥当な金額
環境などと合わせて考えるとコスパは良いと判断できる
日本大学医学部の入試形式
入試形式(2020年度)
| 形式 | 募集人数 |
| A方式 | 97名※ |
| N方式第一期 | 10名 |
| 校友子女入試 | 3名 |
| 計 | 110名 |
※定員120名内で調整を行う場合あり
日本大学医学部の入試形式解説
表でも示した通り、日本大学医学部の入試形式は大きく分けて三種類。
N方式、A方式、校友子女入試の三種類になります。
日本大学は総合大学であり、その影響もあって、試験日が他学部と同じ日にちになっています。A方式は他大学における一般入試、N方式はA方式よりも先に行われる推薦・AO入試のようなものと考えると分かり易いでしょう。(正確には推薦・AOではありませんが)
また、校友子女入試制度も設けられており、二親等以内に日本大学の校友がいる場合に適応され、三名の枠を与えられています。
すなわち、ある程度出願の母数を押さえることで、日本大学医学部に入学できる可能性を高めることが可能であるということです。
ただし、校友子女枠を志望した場合はA方式の出願ができないため、この点は注意が必要です。
各入試形式の合格最低点(2019年度)
| 合格最低点 | A方式 | N方式一期 |
| 一次試験 | 232.4/400 | 237.4/400 |
| 二次試験 | 257.9/430 | 266.1/430 |
| 最終得点率※ | 60.0% | 61.9% |
※二次試験での合格最低点得点率を用い、小数第2位を切り上げて計算。
詳しい試験形式の情報はこちら(https://www.med.nihon-u.ac.jp/examinee/)で最新の情報を得られますので、こちらを頻繁にチェックすることもお勧めです。もちろん当サイトでも変更確認され次第、随時更新します。
このデータからは、大体二次試験まで含めると6割前後がボーダーラインとなっていることが分かります。
これは、私立医学部の入試合格最低点において標準的な得点率であり、ここから問題の難易度自体も、とびぬけて難しいわけでないであろうことは予想ができます。
また、募集人数がそもそも少ないことも相まってN方式第一期の合格最低点はA方式よりも少々高めになっています。
ただし、大きく変化しているわけではないため、両方式の試験の難易度差はそれほど大きくない、ということが分かります。
日本大学医学部の入試形式はここが特徴的!
まず、他の大学であれば推薦入試と一般入試の間に十分な期間(二週間以上)を空けていることが普通ですが、日本大学医学部の場合、A方式とN方式第一期の間に約一週間の期間しか空けられていません。※2020年度入学試験実績
したがって、両試験を受験する場合は、あまり準備期間を取ることができないことが特徴的です。
つまるところ、たっぷりと入試対策を取るのであれば、事前に十分なだけの対策を行っておき、短い時間でもしっかりと対策・対応を取ることができるようにしなければなりません。
もちろん、「日本大学医学部の入試感覚を忘れない絶妙な間の空け方」ととらえることもできますから、感覚を忘れないうちに日本大学医学部の入試をすべて受け終えておきたい、という方には非常に良い試験形式であるといってよいでしょう。
ただ、医学部受験をするにあたり、複数校受験する場合は、日本大学医学部以外の大学を当然受験することになるでしょうから、それら他大学との兼ね合いも考えながら受験することになります。
日本大学医学部の入試攻略
各科目難易度
| 科目 | 英語 | 数学 | 生物 | 化学 | 物理 |
| 難易度 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 形式 | マーク | 記・マーク | マーク | マーク | マーク |
| ※2017年度入学試験を参考に分析 |
※データは(https://www.melurix.co.jp/kouryakuhou/3000/)より引用
解答形式は基本的にマーク式
日本大学医学部の入学試験の解答方式は、数学を除きすべてマーク式となっており、非常に特徴的であると言えます。
なお、科目自体は他の大学と同様に英、数、理の三科目構成となっており、理科は物、化、生の三つから選ぶことが可能になっています。
試験時間
| 入試形式\科目 | 英語 | 数学 | 理科 |
| A方式 | 75分 | 75分 | 120分 |
| N方式第一期 | 60分 | 60分 | 120分 |
| 校友子女入試 | 75分 | 75分 | 120分 |
試験時間については、少し注意が必要で、A方式及び校友子女入試は共通で英語・数学が75分間、理科が二科目合わせて120分間になっています。
対して、N方式第一期の試験時間は理科は他と共通で120分間、英・数が60分間ずつとなっています。
入試攻略方法
英語
日本大学医学部の英語は他大学と比べ非常に特徴的です。
それは、『医学系の英文』が多く、かつ『問題文がすべて英語』であるためです。
他大学の英語であれば、問題文そのものは英語であっても、「~を答えよ」などのように設問部分は日本語であることが多いですが、日本大学医学部では、設問含めすべて英語。
問題用紙中で日本語が使われているところは注釈と、表紙のみ。それ以外は全て英語で記述されています。
この傾向は2017年度入学試験から現在まで続いており、全文が英語、設問も英語の試験問題には慣れておかないと本番で焦ってしまうかもしれません。
また、もう一つ特徴的なのが医学系の英文が多いということ。私立医学部ではありがちな問題形式ではありますが、結構がっつりと医学を問うてきているのは珍しいです。
対策としては、医学英語系のニュースサイト、特に日本語訳が付されているものを普段から読んでおくこと。
また、英検などの過去問は、設問含めすべて英語である場合があるため、英検の過去問を買って読み進めるということもいい対策になります。
もちろん、日本大学医学部の過去問は端から端まで読み込んでおくべきです。
また、長文読解が多いため、文章の流れを何となしにでも把握できるような国語力があるとなおよいでしょう。
日大医学部の英語はここ最近問題文ALL英語がトレンド
普段から長文を読み込める体力をつけるべし
数学
日本大学医学部では、指数対数、数列、積分がほぼ毎年出題。特に積分は数Ⅲの範囲であり、医学部受験でなくとも最も差がつきやすい分野。浪人生であれば手堅く落とさず得点に結び付ける。現役生であれば、浪人生との差を埋めるために、数1A・2Bで多く点を取りに行くなどの戦略が有効でしょう。
形式はマーク式ですが、これまで行われてきたセンター試験以上の難易度を各小問が誇っています。
また、例年試験時間のわりに問題数が多く、トロトロと解いているといつの間にか解答時間が終了してしまい、残念なことになる可能性が大いにあります。
したがって、捨てるべき問題は捨て、受験生の多くが獲ることができる問題を確実に拾っていくという、問題選択のセンスが問われます。
対策法としては、普段からランダム性を高めて問題集にとり組む、時間を計るなどして意識して時間感覚を身に着ける、などが挙げられます。
ランダム性を高めて問題集に取り組むとは、チャートやフォーカスゴールドなどのいわゆる『寄せ集め型』問題集のパッと開けたページを解いていくという方法のことを言います。
また、普段からタイマーなどを使って時間感覚を身に着けておくことです。
例えば、75分の試験時間なら、60分で解き終えて残り15分は見直しに使う。逆に75分全部使っていいから確実に一問一問点を取りに行くなどの実践戦略は、時間ありきの戦略です。
ですから、実際に時間を計りながらでないと細かいところまでは身につきません。
時計で測るというのももちろん一つなのですが、私のおすすめとしてはタイマー。
ボタンも大きく視認性も高い液晶を持っていますから、時間を見間違えることが少なく、非常に有用です。
お勧めのタイマーに関してはこちらの記事でご紹介しています。
もちろん、日大医学部を受けるにあたり数学が不安だという方、数学がネックになりそうという方は、基礎から着実に実力をつけてから、各大学の対策を練っていけばいいことになります。
基礎をつけるには、着実に一歩ずつ進んでいくこと。先ばかり見ていると、目標が遠すぎて、やる気を失いかねません。
もちろん、日本大学医学部に合格するんだ!という目標は大いに掲げていなければいけませんが、それ以前に数学の基礎を固めるということを第一に取り組んでいってください。


日大医学部の数学は時間が勝負
捨てるべき問題は捨てる。拾うべき問題を確実に拾う。
生物
日本大学医学部の生物は、毎年決まった範囲からの出題があるわけではなく、実にランダムに出題されています。
難易度としては非常に標準的なのですが、応用を利かせなければ解けない問題が多いため、少しひねった問題にまで対応できる力が必要になってきます。
なお、どの私立医学部にも言えることですが、やはり医学分野に大きくかかわってくる科目が多いことから、問題も最新の研究の傾向を踏まえたものが多く、これまた最新の研究情報などを知っておくと一歩先まで進めるかもしれません。
対策としては、豊富な知識を事前に蓄えておくこと。そして、最新の研究結果を知るにはナショナル・ジオグラフィックやニュートンなどのサイエンス雑誌を読んでおくことが良いでしょう。
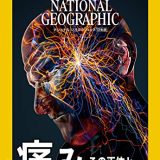
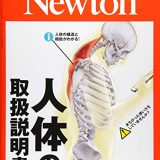
生物において、豊富な知識を蓄えるとは、もちろん断片的に生物学的事象を暗記していくというのも正しいやり方ですが、それらの断片的な知識を最終的にはリンクさせていかなければならないことを考えると、最初からストーリーとして暗記をしておくと、かなり豊富な知識を暗記することができると思います。
そういったストーリー型で覚えるのに最適なのが、生物の図録と辞書型生物参考書です。
この二つの参考書については下の記事でお勧め理由から、使い方まで解説していますので、ぜひお読みください。
豊富な知識がついたなと思ったら、やるべきことはもう多くありません。
知識を再確認するための復習をひたすら行っていきます。
例えば、参考書を周回し終えて飽きたならば、次は大学の過去問を解いていくであったり、幅広い知識を確認するためにセンター試験の過去問を解いていくであったり。
このあたりの細かい生物の勉強法は別記事で死ぬほど詳しく解説していますので、ぜひお読みください。
日大医学部の生物は幅広い知識が要求される
応用の利く知識のつけ方を普段から意識すべし
物理
日大医学部の物理は、難易度こそ総合的には標準であるものの、並々ならぬ知識量と高い応用力を求められるため、油断は禁物です。
そして、選択問題でマーク式ではありますが、複雑な数式を解いたうえで出てくるであろう多くのパターンの解答が選択肢となっているため、答えを急げば間違えた選択肢を選んでしまう可能性が高いです。
2016年度までの入学試験は比較的スピードを求められる問題が多かったのですが、2017年度から現在までの傾向としてじっくりと考えさせる問題が多くなってきています。
対策としては、似たような問題を出題している他大学の過去問を解き、短時間のうちにでも考えさせるような問題を経験しておくことです。また、紛らわしい選択肢を選んでしまった場合にあとから修正することができる『見直し』の能力も高めておく必要があるでしょう。
化学
日本大学医学部の化学では、無機化学の『金属元素』、有機化学の『脂肪族』が頻出の範囲となっています。
無機化学の金属元素に関しては、完全に暗記ゲーになっていますので、ここで点が取れないのはなかなか痛い結果になってしまいます。
有機化学に関しては、化学の中では比較的ロジカルでこちらはパズルのように解き進めることができることから、こちらもできるだけ得点源にしておきたいところです。
化学では代表的な参考書に重要問題集が挙げられますが、こちらはある理由で当サイトではお勧めしていません。
その理由と、別のおすすめ参考書については下の記事をご覧ください。
また、日大医学部化学の特徴として、計算問題の量がかなり多いということが挙げられます。化学の計算問題に関しては、数学が苦手な方でも計算問題を「間違うことなく」解いていくことができれば、高得点率を稼ぎ出すことができますから、落としたくないものになります。
いざ本番になってから、計算問題に臆さないように、普段から計算問題の多い化学の文章題を解き進めておきたいものです。
日大医学部化学は無機、有機ともに落としてはいけない問題が多数
計算問題が多いため、普段から計算問題を解きなれておくべし
まとめ
日本大学医学部は、90年を超える伝統をもち、数多くの優秀な医師を世の中に送り出してきた優秀な大学です。
入試形式は、他大学の医学部と同様に難易度が高く、通常の医学部受験の勉強をしてきた方であれば、努力して受かるレベルの医学部であると言えます。
合格に近づく第一歩はまず大学を知るところから。
是非ともこの記事を隅々まで読み込んで、日ごろから努力を欠かさないようにしてください。
日本大学とレベルが似ている医学部はこちら↓