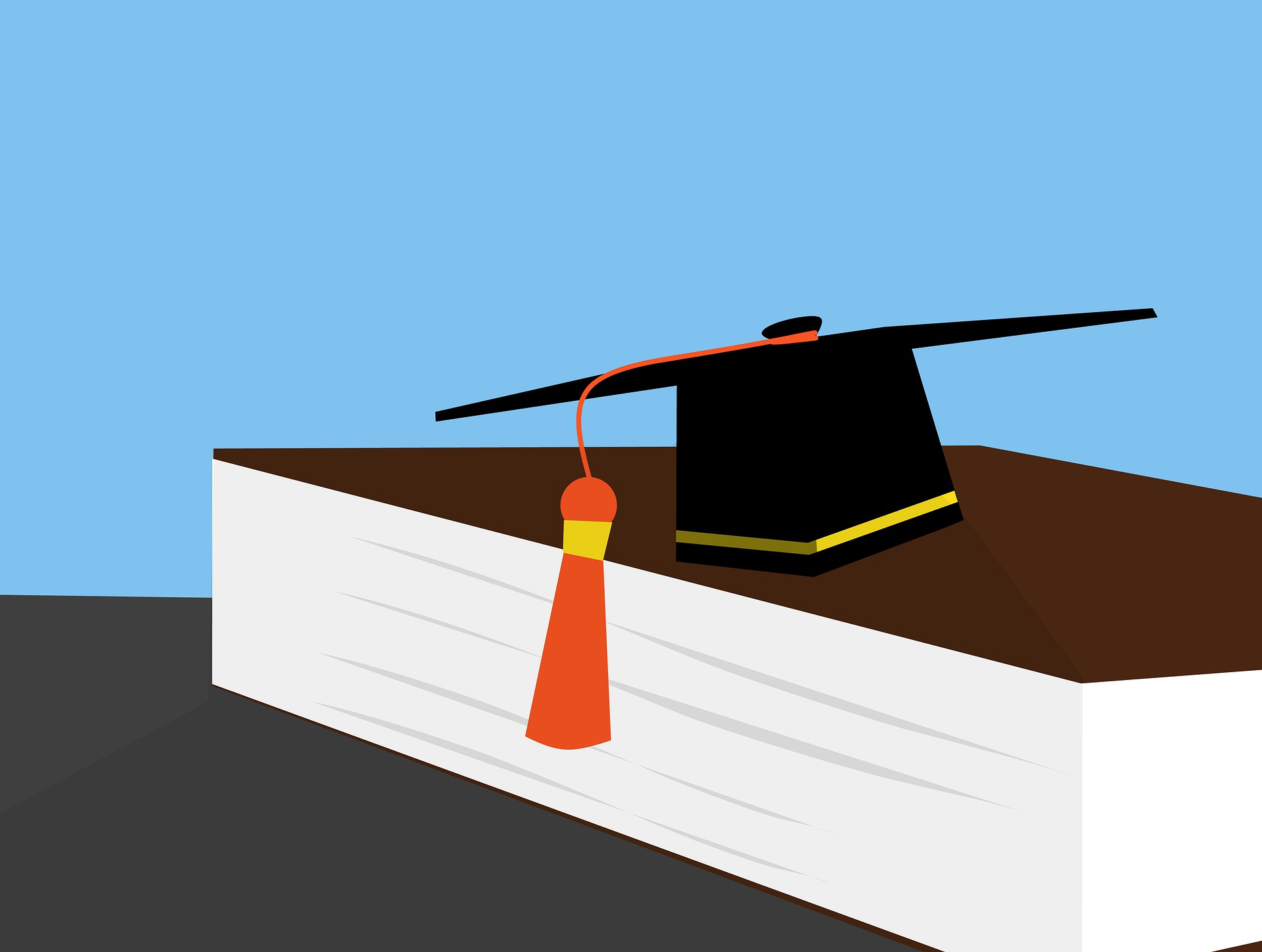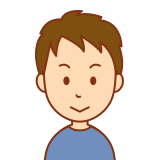
医学部志望として、今受けるべき模試ってなに?あと、高校の先生から強制的にある模試を受けさせられるんだけど、それはいいのかな?
医学部受験生が受けるべき模試も詳しく知りたいなぁ。
こういう人向けの記事です。
・医学部受験に模試が必須な理由
・医学部受験をする場合に受けるべき模試2つ紹介
・模試を受けた直後にすべきこと
筆者(おGちゃん)の医学部受験の経験と、指導してきた経験から深堀しているので、ぜひ最後までお読みください。
医学部受験には模試が必須な理由
残念ですが、これまで模試を受けて来なかった方には悲報です。
模試を受けなければ、医学部への合格率が大きく下がります
上記のように、模試を受けなければ医学部への合格率が下がります。
では、なぜ合格率が下がるのか。
その理由が以下。
・つぶすべき苦手な範囲が見えない
・本番慣れできない
・時間感覚を磨けない
上記の通り。それぞれ、理由を解説していきます。
つぶすべき苦手な範囲が見えなくなる
医学部受験に限らず、勉強に必要なスキルは「自己修正」この一択です。
例えば、英語の成績が上がらないからと言ってがむしゃらに英単語を覚えたとしても、本当は読解力が乏しいことが原因で、英語は一生できないままかもしれない。
自分の「どこが」悪くて「どうやって」直していけばいいのか分からなければ、結局は成績も上がりません。
そういった意味で、「悪いところを発見できる」模試というのは非常に有用。
模試の成績表 → 自分の悪いところが一目でわかる
医療で例えると、自分の悪いところを見つけるための検査のようなものです。
検査をやらなければ、治るものも治りませんよね。
本番慣れできない
医学部受験では、コンマ1点の差が合不合の差を生み出します。
その差は、学力はもちろんですが、試験中の集中力やどれだけ問題形式に慣れているかということでも開きます。
そんな中、模試を受験すると、少なからず本番と似た緊張感の下で問題に取り組むことができるため、緊張に慣れることもできますし、緊張したらどうするかなどの対策を早くから行うことができます。
模試を本番と同じ状況下で受験する → 本番で焦ることなく自分の本領を発揮できる。
模試を受験していなければ、本番になって急に緊張で腹痛が生じることが分かったとか、頭が真っ白になってできる問題が解けなかったなどの事態に陥ることがあるため、要注意です。
つまり、医学部受験本番になって急に実力が落ちてしまうという現象が発生してしまうわけです。
時間感覚を磨けない
医学部受験のにおいて大切なことの一つに「時間感覚」が挙げられます。
受験生の皆さんは、普段から学校の定期試験などで「時間が足りな」くて悔しい思いをしたことはないでしょうか?
誰しもが一回は経験する、時間が足りなくなる現象は、緊張下においてかなり効率よく時間感覚を身につけることで防ぐことができます。
普段は経験することのできない緊張感を味わうことができるのが「模試」ですから、これは受けない理由がないでしょう。
緊張感の元問題を解く → 時間感覚が身に付きやすくなる
模試を受けなければ、だらけがちな普段の問題集を解く時間などで「時間感覚」を身につけなければならないですから、かなり手間になってしまいます。
本番中に、時間配分を間違えて「あと一問あっていれば合格していたかも!!」のような公開をしてしまうかもしれませんしね。
では医学部受験生はどの模試を受けるべきなのか?【2選】

結論から言いますと、医学部受験生が受けるべき模試は以下の二つのみ。
・河合塾全統模試(記述・マーク両方)
・駿台全国模試(最初の一回)
逆に受けるべきでない模試は以下。
・ベネッセ系の模試
・代ゼミ系の模試
・河合塾「医進模試」
・駿台全国模試(第一回以外)
・メディカルラボ「私立医学部模試」
etc...
以上が受けるべき/受けるべきでない模試の一覧になります。
皆さんの良く知っているような模試も含まれていますが、それぞれ理由を解説していきます。
〇河合塾全統模試(記述・マーク両方)
受験母数が多い
受験者層に偏りがない
価格がリーズナブル
難易度が標準的
模擬試験にとって命となるのは受験者の母数です。
河合塾全統模試(以降全統模試)は延べ受験者人数が290万人と、全国の試験の中でもトップクラスの受験者数を誇ります。
そのため、同年代の大学受験者がほぼ全員受験するといってもよく、自分がどれ位の成績レベルなのかが、明確にわかります。
医学部を受験する層もほぼすべてが受けているといっても過言ではないため、受けない理由がないといっても過言ではありません。
また、多くの人数が受けるため、基本的に受験者層に偏りがありません。
非進学校も進学校も、現役生も浪人生も多くの人数が受けるため、自分の成績がどのくらいかということもほぼ正確に判断することができます。
そして、受験者数が多いため料金も6000円~と、比較的リーズナブルとなっています。
加えて、大学受験の模試でありがちな、「難易度の乱高下」が比較的少ない模試でもあり、全体的に完成度の高い模試になっています。
つまるところ、難易度が標準的で、取り組みやすいということです。
医学部受験に「とびぬけた難易度の問題を解ける能力」は全く必要ありません。
それよりもむしろ、難易度が易しめな問題をいかに落とさないかの方が重要です。
そういった意味で、難易度が標準的で、かつ一年を通して変化のない全統模試は医学部受験生には最適な模試であると言えます。
〇駿台全国模試(第一回)
受験母数が多い
難易度が比較的平易
良問が多い(奇問も一部出題)
さすが二大予備校の模試というだけあって、受験母数が多いです。
しかしながら、受験者層という点では「理系が多い」であったり「進学校の受験が多い」であったりと偏りが激しめです。
そのため、正確な自分の成績の位置を計るというよりも、模試慣れするという意味で、また自分の偏差値を概算したい場合には受験することをお勧めできます。
駿台全国模試第一回に関しては難易度が後2回の模試と比較して簡単(それでもムズイ)で、受ける価値があると言えます。
全統模試のところでも説明しましたが、医学部受験に「とびぬけた難易度の問題を解ける能力」は全く必要ありません。
後二回の駿台全国模試は、後で説明しますが「医学部受験生が」受ける必要は全くありません。
第一回目は方針なのかわかりませんが、いわゆる「難問・奇問」が少ないです。
(ほかの駿台模試は講師や作問者の趣味嗜好が色濃く出ていることが多い)
ですから、自分がどの範囲ができていないのか、精査するためには最適な模試であると言えるでしょう。
✖医学部受験生が受けるべきでない模試
一方の受けるべきでない模試はまとめて解説。
・ベネッセ系の模試
・代ゼミ系の模試
・河合塾「医進模試」
・駿台全国模試(第一回以外)
・メディカルラボ「私立医学部模試」
etc...
上記が受けるべきでない模試に当たりますが、これらは何故「受けるべきでない」のか?
それは以下の理由から。
・母数(受験者数)が少ない
・受験者層に偏りがある
・問題のレベルが高すぎる/低すぎる
以上の通り。
それぞれすでに説明していることではありますが、もう一度詳しく説明します。
母数が少ない
模試を受ける目的の一つが、「自分自身の成績の位置を全体の中で確認する」ということ。
受験者がそもそも少なければ、成績が出たところで正確な位置を把握できませんよね。
挙げた模試の中では、代ゼミ系やメディカルラボの模試がそれにあたります。
特に代ゼミは近年縮小してきている予備校で、模試に関してもかなり受験者数が減っていることから受験するのはあまりお勧めできません。
受験者層に偏りがある
模試を受けるメリットが、大学受験とほぼ同じように、全国の様々な受験生と成績を比較することで立ち位置を確認できるということでした。
すなわち、受験者層が偏っているとそもそものデータにも偏りが生じるということ。
挙げた模試の中では、ベネッセ系やメディカルラボの模試がそれにあたります。
ベネッセに関しては大手でかなり多くの受験者数を稼いではいるのですが、何せ受験者のウェイトが国公立高校に偏っており、いわゆる有名私立の進学校はほとんど受験していません。
医学部受験の場合、受験で競争すべき相手はほとんどが有名私立の進学校に当たるため、受験は避けるのが無難でしょう。(ただし、問題自体は良問が多いので経験するのは悪いことではない)
問題のレベルが高すぎる/低すぎる
模試のレベルが極端に高かったり、低かったりすると極端にできる/できないひとに有利に働いてしまうため、正確なデータが取れません。
したがって、極端に簡単/難しい場合は受験を避けるべきでしょう。受けるだけ時間の無駄になってしまいます。
何度も言うように、医学部受験には「難易度の高い問題を解ける」能力は必要ありません。
標準的な問題を人並みに、もしくはそれよりもちょっと多く解けるようになっておくのが鉄則です。
そういった意味で、挙げた模試の中では駿台全国模試(二回目以降)、全統模試(医進模試)は難易度が高すぎて、受験するのはお勧めできません。
また、メディカルラボの模試については、受けるか否かの選択の前に、受験の検討自体をやめて得おいた方が良いでしょう。(そもそもが内部の学生向けの模試)
ただし、メディカルラボの出す医学部受験の情報に関しては、さすが医学部専門予備校と言えるだけの情報の多さ/質の高さがありますので、情報を手に入れるためだけに活用することはお勧めできます。
模試を受けた直後にすべきこと

模試を受けた後にやるべきことはたくさんありますが、直後にやるべきことは二つだけ。
それが以下。
・各問題の分類
・自己採点
以上の二点が、模試直後にすべきことです。
それぞれ解説していきます。
各問題の分類
模試は受けるだけでは効果がありません。
普段の勉強で問題集を解くだけ解いても何の成長もないように、模試も受けるだけ受けても血肉にはなりません。
そこで、模試をうけた後にやるべきことは復習でしょう。
模試の復習方法などの記事は後日合わせてアップするので、ぜひお読みください。
そのための準備を、模試が終わった直後から始める必要があります。
それが「解いた問題の分類」です。
各小問ごとに「できた」「できなかった」「そもそも解く時間がなかった」などと簡潔に分類していきます。
それぞれの問題の番号などに自分だけが分かるようなマークを記入していくと、より分かりやすいです。
この分類を、模試の内容を忘れないうちに行っておくのが、模試を復習するときのミソになります。
自己採点
本番の受験であれば、問題を解いた後に自己採点をするというのが普通のこと。
その練習をするためにも、模試を受けた直後の自己採点はお勧めです。
気を付けるべきは「帰ってきた成績表との差がないかどうか」。
自己採点と実際の点数が違う場合、本番でも同じような採点のミスを犯してしまうかもしれません。
センター試験(共通試験)など、点数が直接志望大学を左右する場合に大きく響いてくるため、自己採には慣れておきましょう。
『忘れないうちに』採点をするというのが、間違いなく自己採点をする上で大切です。
まとめ
模試は医学部受験に必須です。
どんな大学に入るにせよ、入試を突破するには慣れと知識が必要になります。
医学部受験生がこの記事で受けるべき模試が分かり、受験の助けになればいいなと思い記事を書きました。
是非、医学部受かってください。