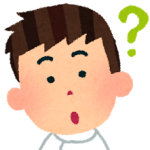
医学部で一番心配な解剖なんだけど、試験で落ちたくないし、効率的にたくさんの情報を入れたいなぁ。
どういう参考書なら、効率的に知識を入れられるの?あと、おすすめの参考書も教えてほしい。
こんな悩みに答えます。
・解剖の成績が参考書一つで大きく変わるワケ
・解剖の参考書を選ぶポイント
・おすすめ参考書徹底比較
この記事を書いてる僕は医学部3年生。
2年生の頭から約3か月間、解剖を勉強してきましたが最終的には学年上位20%に入るだけの成績を取ることができました。
ここで紹介する参考書は、僕が実際に使って厳選してるので、ある程度信頼できると思います。
解剖は参考書一つで成績変わる

医学部で難関と言われる科目、それが解剖です。
難関と言われるゆえんは様々ですが、そのうちの最も大きな一つが「イメージしにくい」ということ。
僕たち医学生は実際にご遺体を解剖して、体の構造を勉強していくわけですが、正直、最初はイメージしがたい構造物ばかりで、なんのこっちゃ分かりません。
神経の走行位置であったり、骨と筋肉の接地点であったり、血管の配置など本当に複雑。
こういったイメージしにくい構造物の形などを覚えていくには、やはり何かしら資料がなければ不可能に近いでしょう。
この時に重要になってくるのが、アトラスなどの参考書です。
参考書に載っている解剖図を参考に、解剖をすればしっかりとイメージもわきますし、臓器同士の配置も理解しやすいです。
イメージがしっかりとできるようになれば、解剖の知識もすっと頭に入ってきますから、参考書の存在は本当に大切。
つまり、成績は参考書一つで簡単に変わってきます。
解剖自体の勉強法はこちらの記事を参考にしてください


解剖学の参考書を選ぶポイントは3つ

そんな解剖に必須ともいえる、参考書を選ぶポイントはたったの3つ。
それが以下。
・情報量の多さ
・図の分かりやすさ
・最新版か否か
以上の3点です。
どれもとても大切なポイントなので解説していきます。
情報量の多さ
どんな参考書でもそうですが、知識が多くないと枝葉の知識まで身に付きません。
例えばですが、単に骨の知識だけ、筋肉の知識だけあったところで、
どうやって体を動かせるのか?
というところまでは理解が及びません。
「骨の○○にこの筋肉がついているから、こういう動きをする。」と、知識が体系づけられて初めて解剖の知識として成立するわけです。
つまり、単に解剖の図しか載っていない参考書は使えない。どれだけ細かな知識が分かりやすく描かれているかが重要です。
したがって、「それぞれの知識を体系づけられるだけの情報量があるか?」というのが参考書を選ぶ一つ目のポイントになります。
図の分かりやすさ
どれだけ情報量が多くとも、知識として取り入れやすいように図が描かれていなければ、勉強するときに不便です。
いちいちネットを調べたり、別の参考書を引っ張ってきて「ここはいったいどうなっているんだ?」と調べる手間が生じます。
本当に使いやすい参考書はその一冊だけで、解剖の知識を体系的に整理できるものです。
立体的に体の構造をとらえやすかったり、他の構造物との関係性をしっかりと確認できる図であったり、やはり理解を深めるにはわかりやすい図が掲載されているものがより良いでしょう。
最新版か否か
医学の中でも解剖学は比較的情報の更新が少ない分野かもしれません。
しかしながら、解剖学の参考書に関しては常にその時代の医学生に合わせて進化していますから、一見同じように見えても、実は版が変わればわかりやすい図に入れ替わっていたりします。
また、情報の更新が少ないとは言いましたが、最近の医学の進歩はすさまじく、それに合わせるように内容も更新されていきます。
例えば構造物の名称が昔のものと違うだとか、血管の走行パターンが増えているとかは、細かいところでやはり最新の参考書の方が勉強に有利であると言えるでしょう。
おすすめ参考書徹底比較
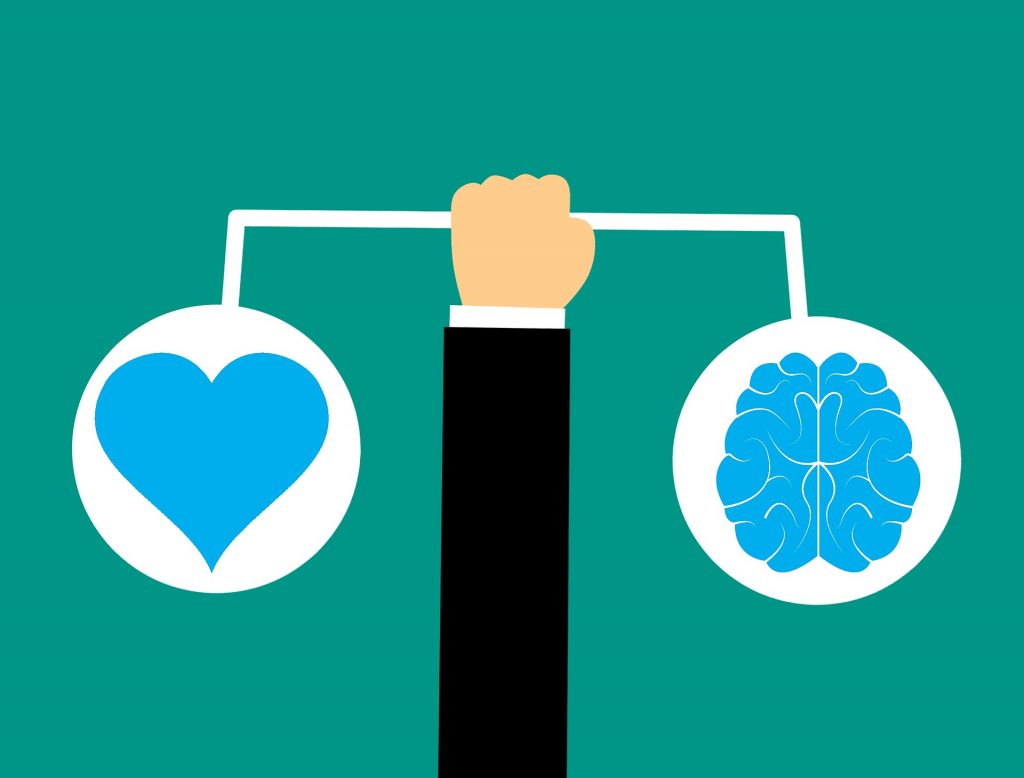
では、さっそく解剖学の勉強におすすめの参考書を徹底比較していきます。
今回比較していくおすすめ解剖参考書は以下の5冊です。
・グレイ解剖学
・ネッター解剖学アトラス
・プロメテウス解剖学コアアトラス
・解剖学カラーアトラス
・イラスト解剖学
上記5冊です。
正直に言って、解剖学の勉強に上記以外の参考書は使ってはいけません。
他の参考書はどれも情報が古かったり、図が見にくかったりで勉強には使いづらいためです。
使うなら、ここで紹介するような、しっかりと版が重ねられて情報に正確性のある書籍を使うべきでしょう。
以下、これら参考書のおすすめの理由とそれぞれを徹底比較していきます。
グレイ解剖学
2019年9月に最新版がでたグレイ解剖学。
これまで四回にわたる内容の刷新をしてるので、かなり内容は練られており分かりやすいです。
僕も何度か使っていましたが、情報量の多さが他に比べて群を抜いており、知識の取入れにはうってつけと言えます。
図は少し癖のあるイラストを使用しているため、初めて使用する場合は少し慣れが必要かもしれません。
他にもアトラスバージョンがありますが、こちらの本の説明を省いただけなので、アトラスを買って無駄に重くなるなら、この本一冊を持っておけばいいと思います。
また、近年流行りつつある「iPad勉強」用にも電子書籍がついているので、iPadを使った勉強をする場合にも使いやすいです。
情報量の多さ:5点/5点
図の分かりやすさ:4点/5点
ネッター解剖学アトラス
親切にも学習の手引きがセット販売されているネッター解剖学アトラス。
エルスビアという電子書籍アプリに対応しており、iPadでの勉強の際にも非常に役立ちます。
図の分かりやすさは今回紹介する参考書の中ではトップクラスで、体の構造に関するイメージをつけるには非常に有用です。
他の参考書に比べて文字情報が少なめですが、それを補って余りある図の分かりやすさがあり非常に使いやすいです。
ちなみに、僕は他の参考書と使い比べて、このネッターが一番しっくり来たため、解剖の勉強中はずっとこれを使っていました。
情報量の多さ:4点/5点
図の分かりやすさ:5点/5点
プロメテウス解剖学コアアトラス
解剖学の参考書と言えば「プロメテウス」と言われるほど、非常に有名な参考書です。
解剖図がCGによって作成されており、非常に美麗であることで勉強の初めにはとっつきやすいため、よく使われるようです。
ただし、イラスト中心の参考書であるため情報量が少々乏しいです。
また、図もきれいではありますが本物の身体を理解するときにはこの一冊だけでは少し使いにくいかもしれません。
コアアトラス以外にも、運動器、脳神経など別個のジャンルで出版されているため、プロメテウスにこだわる場合は、それらを購入してもよさそうです。
情報量の多さ:3点/5点
図の分かりやすさ:4点/5点
解剖学カラーアトラス
今回紹介する解剖の参考書の中では唯一、本物のご遺体を使ったアトラスになります。
情報の多さ、図の分かりやすさともに他の参考書には劣りますが、実際の身体に準拠した内容となっているため、実際に解剖しているときに使うならこの参考書は本当に使いやすいです。
また、イラストだけでは表せない色のコントラストも写真で表現できるため、細かい構造物の把握がしやすいです。
そのため、他のアトラスを持ちながらもこのアトラスを購入して、知識の結びつきを強める医学生も多いです。
情報量の多さ:3点/5点
図の分かりやすさ:3点/5点
イラスト解剖学
杏林大学医学部の教授さんが、日本の医学生の為だけに豊富な手書きイラストを用いて作られた参考書です。
今回紹介する5冊の参考書の中では唯一説明型の参考書で、知識の体系づけが効率的にできます。
図が手書きであるということもあり、人によって合う合わないがあるとは思いますが、略図などを用いて詳しく構造解説がなされているため、体の立体構造を理解するのに非常に役立ちます。
また、知識を深めるのに役立つ豆知識や、覚えるときに躓きがちなポイントが簡潔に分かりやすく整理されているため、勉強のお供に最適です。
2017年の版が最新版の為、すこし不安感は否めませんが、「立体構造をとらえやすい手書きのイラスト」というジャンルでは他の参考書を圧倒しています。
情報量の多さ:4点/5点
図の分かりやすさ:3点/5点
各参考書の方向性をまとめてみた
それぞれの参考書の特徴をまとめると以下のようになります。

以上のように、「グレイ」「ネッター」「プロメテウス」が同じジャンルで、「カラーアトラス」「イラスト解剖学」が異なるジャンルに位置します。
まとめ
最終的に僕が「参考書を迷っている人」にアドバイスするなら、
解剖図がイラストの「アトラス」どれかと、イラスト解剖学の二冊持ちがおすすめだよ
と言うと思います。
解剖の勉強には、図が分かりやすいアトラスで構造物のアバウトな位置を理解したうえで、イラスト解剖学を使ってそれら知識を紐づけることが一番効率がいいからです。
ただ、個人個人であう参考書/合わない参考書はあると思うので、実際に中身をみて決めることをおすすめします。













