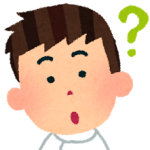
医学部の解剖実習ってどんな感じなんだろう。大変だって聞くけれど本当に大変なんだろうか?
気分が悪くなってしんどいのかそれとも単純に実習自体が大変なのか知りたい。
後は、これから経験するにあたって、実際に解剖実習を体験した人の感想を聞いて、どうやって乗り越えればいいのか知りたい。
このような疑問に答えます。
・医学部の解剖実習が実際どんな感じなのか
・医学部の解剖実習で本当に大変なこと4つ
・解剖実習を乗り切った経験談&ポイント
上記のような内容で記事を書いていきます。
ちなみにこの記事を書いている僕は2019年に解剖実習を経験しました。
解剖実習には、実際にやってみないと分からない「大変な」ことが沢山あります。しかし、意外にもそういった情報はあまりネット上には出回りません。
事前にそういう情報を知っておけばかなり効率的に実習に挑めますし、僕自身もやる前に知っておきたかった情報が多数あったので、この記事を通じて皆さんにお伝えできればと思います。
医学部の解剖実習ってこんな感じ

医学部の解剖実習の特徴を簡単に3つのポイントにまとめてみます。
✔本物のご遺体を用いる
✔実習期間が数か月
✔特殊な環境下で行われる
以上3つのポイントです。
知ってるよ、という方もいるでしょうがそれぞれ説明していきます。
本物のご遺体を用いる
一番の特徴と言ってもいいでしょう。
日本における法律では、「解剖ができるのは通常保健所に届け出を出した場合のみで、一般人にはできない」と規定されています。
が、その例外として、医学部などの医学系大学での解剖が存在しています。
二 医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000204
つまり、医学生という何の資格も持たない一般人が遺体の解剖をできるというのは、ある種特権として認められているということです。(教授や准教授の指導下に限る)
そして、後にも先にも、「法医学」や「解剖学」などの解剖系の学問に進むのでなければ、これ以降は実際のご遺体を解剖する経験はできません。
CGやデジタル技術が発達した現代においても、実際に五感を使って人体の正常構造を勉強できるという意味で、非常に貴重な経験になります。
実習期間が数か月
医学部低学年で行われる実習のうち、数か月もの期間を使って行われるのは解剖実習だけです。
短いもので2か月。長くて半年もの期間が解剖実習に充てられます。
大学によって行われる時間帯こそ違いますが、この実習が行われている間は生活がほとんど解剖中心になります。
一回の実習時間が3時間以上で、長ければ6時間以上まで及ぶこともあり、長時間の実習という意味でも非常に特徴的です。
特殊な環境下で行われる
解剖実習が行われるのは、通常生活していれば過ごさないであろう環境です。
代表的なのが「気温」と「匂い」です。
ご遺体が腐敗しないように、解剖実習室は非常に低い気温に保たれます。一般的には15℃前後らしいですが、これが結構寒いです。
また、同じく腐敗防止のために「ホルマリン」が用いられているため、非常に匂います。直接体内に吸入すると有害であるため、大抵は特殊なマスクを用いて実習に挑みますが、それでも結構匂います。
このような特殊な環境下において行われることは、解剖実習の特徴の一つです。
また、後述しますが、この実習を大変にさせている原因の一つでもあります。
医学部の解剖実習で大変だったこと

ここからは、僕の経験談を交えながら、実際に解剖実習で大変だったことをまとめていきます。
考えるとけっこうたくさん大変なポイントはありますが、主だったものを上げると以下のようになります。
✔寒い
✔臭い
✔ずっと同じ姿勢
✔グループの人間関係
以上4つです。
それぞれ解説していきます。
寒い
先ほども言いましたが、解剖実習室は腐敗防止のため常に15℃台に保たれます。
実習中は、解剖実習着を着ているため、ある程度の寒さは緩和されますが、そんなに動くわけではないので、基本的に寒いです。
結構これがポイントで、暑いのが苦手な男性等であればいいのですが、寒いのが苦手な女性は結構風邪をひきがちです。
体力が十分あり余った初期のころであれば、さほど問題はないのですが、連日の実習で疲れてきたときに、寒さが結構体に来てしまい、風邪をひく。そんな感じです。
実際に僕と同じグループだった女の子も風邪をひいていました。実習は全て通しで成り立っており、一回でも休むと流れから外れてしまうため、勉強に支障が出てしまいます。
その子は何とか風邪を治して数日で復帰しましたが、もしも長引いていたら、結構なディスアドバンテージになっていたでしょう。
臭い
実習中、ご遺体には敬意を払い、尊敬の念をもって挑みます。
しかしながら、匂いは結構きつく、無視できないです。
匂いのメインは防腐剤である「ホルムアルデヒド」ですが、実習中にはやはりたくさんの匂いを発する物質が出てきます。
何とは言いませんが、やはり医師になるうえで避けては通れないとは思いつつも、匂いは結構精神的に来てしまいます。
解剖中に切る実習着はもちろん、中に持ち込む筆記用具や下着などにも匂いが染みつきます。
洗濯することで匂いは解消されますが、何せ連日の実習であるため、匂いは染みついて取れなくなりますし、使った後の匂いの処理が大変です。
ずっと同じ姿勢
実習中は大抵「椅子に座って前のめりの姿勢」になります。
ご遺体で構造物を同定しようとしているとみんな自然とこの姿勢になります。
が、これを維持しているとけっこう身体にガタが来ます。
腰が痛くなったり、肩が凝ったりと解剖実習を通して、「あれ、俺/私は外科医には向いてないかもしれん」と思ったりしてしまいます。
グループの人間関係
僕の場合、これは大丈夫でしたが、先ほども言ったように解剖実習は数か月にわたって行われます。
その実習中は、5~10人の同じ面子で解剖に挑むわけですが、これが結構曲者です。
同じ面子で、長い期間一緒にいると話したりする機会が多くなるのは自然なことです。その面子で非常に仲良くなったりすることが多いことは事実です。
しかし同時に、仲が悪い間柄がその面子に含まれてしまったり、あるいは実習を通して仲が悪くなってしまった人がいると実習時間が地獄と化します。
僕の隣のグループは、仲が悪い同士が主導権を奪い合っており、何かと喧嘩が絶えないグループでした。
そういうグループに配属されてしまった場合、精神的に疲れてしまう子が何人か見受けられました。
医学部の解剖実習を乗り切るポイント

ここからは、ここまで述べてきた「解剖実習の大変さ」を乗り越えるポイントを解説していきます。
そのポイントは以下です。
✔気温に対応できる服装にする
✔捨てられる服装で挑む
✔一時間に一回立ち上がりストレッチ
✔先生に相談する
すべてそのままの内容ですが、簡潔に説明していきます。
✔気温に対応できる服装にする
「寒い」ことは明白なので、自分で気温に対応できる服装にしましょう。
暑がりならタンクトップなんかでちょうどいいかもしれませんし、逆に寒いなら、ネックウォーマーなんかを付けたっていいでしょう。
基本的に解剖実習着の下に着るものは自由でしょうから、自分の体調に合った服装を選ぶようにしましょう。
ちなみに、僕は寒がりだったので、ユニクロのあったかい下着を重ね着してました。
✔捨てられる服装で挑む
服装に関してもう一つ。
匂いに対応するために、極力実習期間が終わった後に捨てることのできる服装を選びましょう。
時に、医学部にはめちゃくちゃな金持ちがいて、ブランド物の服装で解剖実習に挑む場合があると聞きます。(僕の大学ではいなかった)
もったいないのでやめましょう。
実習で使った服は、実習後には匂いがきつすぎて100%使えなくなります。たとえどんなに匂いが染みつきにくい服でも、数か月実習室内で使えば、立派に匂いが染みつきます。
下着、上着、靴全て、捨てることができるものを選ぶのが無難です。
ちなみに僕は全身合わせて3000円くらいの安い服装で挑んでいました。
買った場所はユニクロや、ディスカウントストア等とにかく安いところでした。
✔一時間に一回立ち上がりストレッチ
同じ姿勢でいると、かなり体力を削られます。
首、肩がかなり凝りますし、何よりずっと同じ姿勢だと気分も晴れませんし解剖の効率が落ちてきます。
一時間に一回は立ち上がって軽くストレッチすることをお勧めします。
もちろん、実習の状況によりますが、大抵、解剖の時間中は自由に立ち上がれると思うので、立ち上がって身体を動かすのがベストです。
✔人に相談する
解決策を述べてきましたが、長い実習の期間中、自分の力だけで解決できないことがあるのも事実です。
先ほど言ったような「人間関係」などは、自分の力で解決できなければ、解剖の先生や親、友達に相談してみるのも手です。
その場合、事実を確認したうえで、どういう風にしてほしいか解決策を自分から提示するのが良いでしょう。
多くの場合、その人が精神的に「キて」いても、外から見ただけではわからないです。
自分から、相談する人に事情を説明し、どうしてほしいかを言ってみるといいでしょう。
まとめ~真剣に挑みましょう~
解剖の実習は大変だったという話、どうでしたでしょうか?
僕なりに結構まとめてみましたが、まだまだ大変なことはあると思います。
その都度その都度、解決策を考えてみるのも、今後の医学部生活に役立つと思います。
また、大変な話を紹介しましたが、解剖はそもそも多くの人が一生に一回しか経験しえない(例外あり)ことです。
この貴重な機会を使って、解剖学の勉強に役立てたり、今後の医者人生に厚みを持たせたり、活用方法は様々です。
ご遺体に常に感謝の気持ちを持って、真剣に解剖実習に挑んでください。
必ず、一生モノの経験が身に付きます。
解剖の勉強法や、お勧めの勉強法は別記事で詳しく解説しています。
合わせてお読みください。






